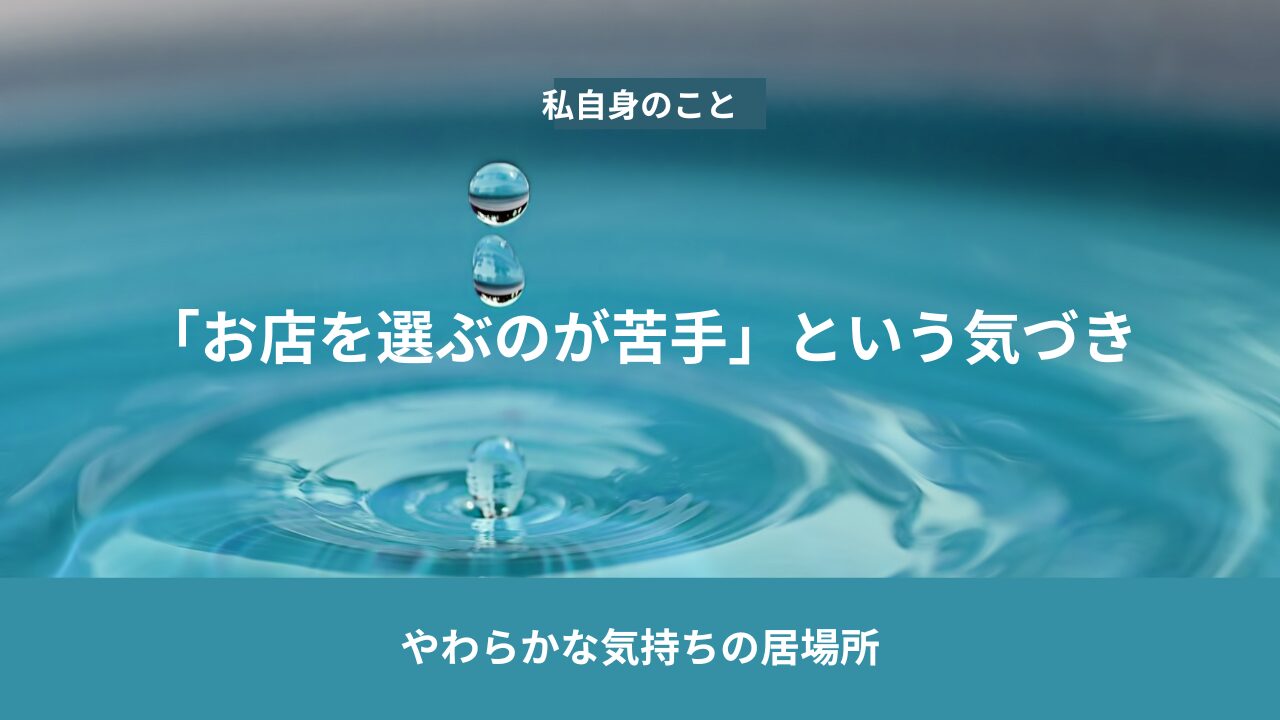私は誰かと食事に行くとき、よく「お店を選んで」と言われて困ってしまいます。皆は「今日は焼肉がいい」「パスタの気分」と明確な希望を持っているのに、私は考えすぎてなかなか決められません。相手に合わせたり、迷い続けたりして結局とても疲れてしまうのです。
最近になって、これは私のASDの特性の一つなのかもしれないと気づきました。ASDの人は選択肢が多いと迷いやすく、完璧な答えを求めすぎる傾向があると聞きます。お店選びは、価格・場所・混雑具合・メニューの好み・雰囲気など考える要素がとても多く、頭がいっぱいになってしまうのです。さらに私は受動的になりやすく、「自分が選んで失敗したらどうしよう」と不安になり、余計に決められなくなっていました。
気づいたからできる工夫
けれども、この苦手さに気づいたことで、少し工夫できるのではないかと思うようになりました。
たとえば、あらかじめお気に入りのお店を3つほど決めておいて、その中から選ぶようにすれば迷う時間が減ります。「今日は静かなお店」「今日は駅近」など先に条件を決めると、選びやすさもぐっと上がります。
さらに「ジャンルを決めるのは私」「具体的なお店を探すのは相手」と役割を分けたり、「イタリアンと和食どっちがいい?」と二択で提案すれば、相手と一緒に選べて気持ちも楽になります。
長男の特性との違い
そんなことを考えていたら、長男とのエピソードを思い出しました。
以前、家族で小さな人気ケーキ店に行ったときのこと。私は自分の食べたいケーキをすぐに決められます。ところが長男は、どんなに混んでいようと何分も考えたいのです。ところが最後は列の後ろが気になり、慌てて選んでしまった結果、後々まで何時間も怒ってしまいました。長男の場合は「食へのこだわり」が強く表れるのです。
それに比べて私は、食へのこだわりはさほど強くありません。むしろ「選択肢が多すぎると困る」「周りの人に迷惑をかけないように選ばなきゃ」という気持ちの方が働くのです。特性の現れ方が違うので、同じASDでも外からは分かりにくい部分があるのだと感じます。
おわりに
お店を選ぶのが苦手なのは性格の弱さではなく、特性によるものだと理解できただけでも心が軽くなりました。これからは「選べない自分」を責めるのではなく、「工夫で補えること」として向き合っていきたいと思います。